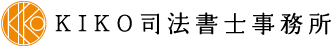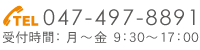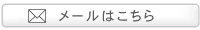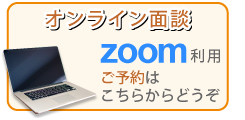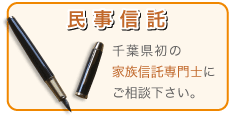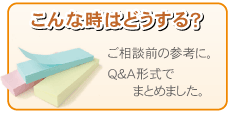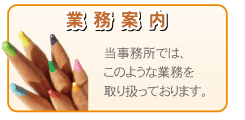‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ
 孫への贈与、税優遇
孫への贈与、税優遇
10/24日経新聞1面より。
相続時精算課税制度の対象が拡大されそうです。
現行、この制度を使えば、65歳以上の親から子供への贈与は2500万円まで非課税。
これを、孫への贈与にも認める方向で検討しているそうです。
いいですね、大賛成です!
高齢化社会ですから、親が80歳、子が50歳、孫が25歳なんていうケースもざらにあります。
80歳の親から50歳の子供に資金をあげるより、25歳の孫にあげた方が、使い道がたくさんありますよね。
これから結婚式、出産、住宅購入、とまだまだお金が必要になる場面はたくさんありますものね。
うちの親は昭和22年生まれですが、この世代の皆様は贅沢をせず、きちんと資産形成をされている方が多く、頭が下がります。
自分が65になった時、ちゃんと、子供や孫に残してあげれる資産があるんだろうか。
ハワイ行きたーい、温泉行きたーい、美味しいもの食べたーい、ばかりではダメですね。。。
反省。。。
 相続人の中に破産者がいる場合
相続人の中に破産者がいる場合
先日、法務省民事局より、こんな通知が届きました。
「相続人の中に破産者がいる場合の相続の登記の申請における相続を証する情報の取扱いについて」
相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、相続人の一人が破産者である場合、通常通り、遺産分割協議ができるのか?
→できない。
破産者自身は遺産分割協議に参加できず、破産管財人が裁判所の許可を受けて、協議に参加する。
分割協議書に押印するのは、破産管財人なんですね。
破産者は、「破産手続開始時に有する財産」の財産管理権を失うので、破産手続開始決定の時にすでに相続が開始していれば、相続財産は、「破産手続開始時に有する財産」になるんですね。
たとえ遺産分割協議が終わってなくても。
なので、その相続財産の管理処分権までも失ってしまうのですね。
相続人の破産については、破産法の改正により色々変わったようです。
一般の方の相続財産のメインは、不動産ですから、司法書士も知らないわけには行かないですねぇ。
少し勉強します(^_^;)
 オンライン申請
オンライン申請
昨日 9月30日は、月末かつ半期の末日ということもあり、不動産の決済や住宅ローンの実行が重なりました。
9月30日は、月末かつ半期の末日ということもあり、不動産の決済や住宅ローンの実行が重なりました。
申請先は、木更津法務局、船橋法務局、世田谷法務局とてんでバラバラ。
ん~、ちゃんと、こなせるだろうか。。。数日前から色々シュミレーションし、密かに一人で緊張してました。
当日、世田谷法務局は決済場所から近かったので、足を運びましたが、他2か所は、オンライン申請です。マックでノートパソコンを開き、公衆無線につなぎ、法務省オンラインシステムにログイン。
そして、ICカードで署名して、いざ、申請データを送信!
最後に、ネットバンキングで免許税を納付。
できた!
外出先でオンライン申請するのは初めてだったので、ほっとしました。
でも、ノーパソだと読み込みが遅く、なんだかんだで1時間かかりました。
不動産の登記申請は、何千万という、大金の決済と連動しているので、何がなんでもその日にしなくてはいけません。
お金を出す方は、抵当権を第一順位でつけることにより、担保保全しているわけですから。
毎回、緊張する場面です。
オンライン申請が始まってまだ2,3年。
厳しい時代に開業したね、とよく言われますが、私には良かったと思ってます。
オンラインの有難さをひしひしと感じています。
ひと昔前だったら、アシスタントを雇わないと、手が回りませんからね。
午後3時過ぎ、やっとお昼ご飯にありつけました~。
もちろん、そのままマックでエビバーガーセットです(^_^;)
 簡裁訴訟代理認定考査
簡裁訴訟代理認定考査
先週、司法書士の認定考査の合格発表があったようですね。
司法書士の仕事の中でも、裁判業務をやるには司法書士試験の他に、この試験に受からないとできないのです。
認定を受けた司法書士には、簡易裁判所において一定の訴訟代理権があります(民事事件・訴額140万円まで)。
私も平成16年に取りました。
が、登記業務が多く、いまだ活用する場面もなく・・・。
登記に限らず、せっかく資格を与えていただいたのだから、困った方の人助けもしていかねばならんなぁ。
開業してから特にそう思います。
何か困ったことがあったら、力になれれば嬉しいです。
一緒に考えましょう。
(今年の認定考査 法務省資料)
 やっと涼しく・・・でも
やっと涼しく・・・でも
いきなり涼しくなりましたね。
事務所も窓を開けて、ノークーラーでお仕事!
といきたいところですが、今週は近所のオートレース開催日・・・
バイクの音が建物にこだまして、ものすごい音になってます。
ここは14階ですが、高層階はもっとすごいとか。
ダメだ、やっぱりクーラーにします(-.-)
 相続対策
相続対策
元気なうちに相続対策、できることはしておきたいですね。
確実なのが、生命保険の非課税枠(500万×法定相続人の数)を使い、払う相続税をなるべく少なくすること。
昨日、知り合いの保険会社の方とお話する機会があり、お得な保険の掛け方を教えてもらいました。
「終身一時払」
終身保険で、保険料を初めに全部払いこんでしまうというのです。
試しに計算してもらったら、私が100万円を一括払いした場合、約180万の死亡保障となり、4年目以降であれば途中解約した場合、必ずプラスになって戻ってくる計算でした。
たしか、5年目で8万円?10万?位だったかな(肝心なところ覚えてなくてすみません。)。
とにかく、元本割れしないんです。びっくりでした。
4年目以降であれば、いつでも解約したい時にできるし。
貯金代わりにいいですよね。
保険会社にメリットはあるのか?と尋ねたところ、4年間にまとまった資金を運用できることだけがメリットだそうです。
これを使って、預貯金がある方は、非課税枠いっぱいまで終身一時払いで保険にしてしまうというのはどうでしょうか。
初めて聞きましたよ!とお話したら、このタイプは営業マンの手数料が取れないらしいです。
なので、あまり勧める営業マンがいないとか。
これからも、相続対策、いろいろ勉強していきたいです。
 続き 税務上の扱い
続き 税務上の扱い
先日の代償分割の登記原因「遺産分割による贈与」のつづき。
さて、税務上はどんな扱いがされるのでしょう?
贈与税? それとも相続税?
調べたところ、譲渡する側(あげる側)に「譲渡所得税」がかかるそうです。
当初、取得した時の価格と、今回代償分割の一環で手放すことになる価値(代わりに得る相続財産の価格相当)との差額に所得税がかかるという事でしょうか。
当初、私は、遺産分割協議とは別に贈与契約をして、と考えていて、実質、不動産の免許税も変わらないし、大した差もないなぁ、
なんて思っていましたが、ここに決定的な差がありましたね!
払う人が違ってきますものね。
 遺産分割による贈与
遺産分割による贈与
遺産分割の方法のひとつに、「代償分割」という方法があります。
ご存じですか?
ふつうは、誰が何を相続するか、相続人間で分割協議しますが、たとえば、財産が「不動産」ひとつだけだった場合、土地や建物を数人で分けることは現実的にあまり得策ではありません。
そんなときに使えるのが「代償分割」という方法です。
「長男が自宅を相続する代わりに、長男は次男にお金を払う」という内容の協議ができます。
こうすると、長男は実家にそのまま住み続けることができ、次男も納得してくれるのではないでしょうか。
もし、支払うべきお金がない場合、お金でなはく、「長男がもともと持っている他の不動産を次男に贈与する」、という協議もできます。
そして、これを登記する場合、その登記原因は、「遺産分割による贈与」になります。
あくまでも相続ではないので、登録免許税は、通常の贈与と同じ固定資産評価×20/1000で高いのですが・・・・。(相続は固定資産評価×4/1000)